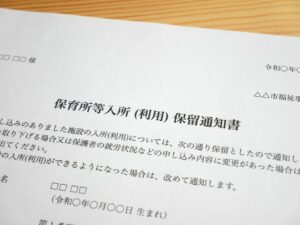現在、政府は「安心につながる社会保障」の取り組みの一環として、2020年代初頭までに介護を理由とした離職の防止を図るべく「介護離職ゼロ」を推進しており、必要な介護サービスの確保と、働く環境改善・家族支援を両輪として取り組んでいます。
政府が撲滅を目指している介護離職の実態や原因、対策を解説します。
介護離職とは?
介護離職とは、家族などの介護を理由に会社を辞めることを指します。
近年、介護離職は社会問題の一つとして取り上げられることが多くなっています。
介護離職の何が問題なのか
年間の全離職者数における介護離職者数の比率は、それほど高くありません。
にもかかわらず、介護離職が問題視される理由は次の2点です。
- 介護を抱えているのは40〜50歳代の企業の中核を担う人が多く、そのような人材が離職すると企業活動に大きな影響がある
- 介護離職した人が再就職することは難しく、離職者が経済的にひっ迫し生活保護を受けるケースもある
これらは国全体の経済活動にも少なからず影響を与えており、介護離職による経済損失は6500億円にのぼるという経済産業省の試算もあります。
そのため、政府は「介護離職ゼロ」を国の目標の一つとして掲げ、介護従事者及び家庭の支援のために環境整備や制度の拡充に取り組んでいます。
介護離職の現状と実態
ここでは介護離職の現状について解説します。
介護離職者の人数
総務省がまとめた「平成29年就業構造基本調査」によると、平成28年10月〜平成29年9月の1年間で、介護・看護を理由に離職した人の人数は99,100人です。
これは、同期間の全離職者の1.8%にあたります。
平成24年に行われた前回の調査では、1年間の介護離職者数は101,100人だったため、前回調査時からほぼ横ばいと言えます。
また、介護を抱えている人の数は627万6千人にのぼり、これは15歳以上の全人口(1億1千万人)の約5.6%にあたります。
15歳以上の全人口のうち、18人に1人が介護を抱えており、112人に1人が1年以内に介護離職に追い込まれていることになります。
介護離職者が増加する懸念も
平成29年の支援・介護を必要とする要支援・要介護者の数は628万2千人です。
その内訳は次の通りです。(単位は万人)

内訳から分かる通り、75歳をすぎると要支援・要介護者の数は急増します。
団塊の世代が75歳に突入する2022年以降、要介護者の数は増えていくことが予想され、それに伴って介護離職者の数も増加する懸念があります。
介護離職者が直面する問題
離職して介護に専念することで、介護者の負担が減って楽になると思われがちですが、実際には介護離職した人は大きな問題に直面しています。
介護離職者が直面する主な問題は以下の3つです。
- 負担が減らない、むしろ増える
- 老後資金が減る
- 再就職ができず、経済的に困窮する
負担が減らない、むしろ増える
介護に専念することで、精神面・体力面の負担が減ると考えがちです。
しかし実際には、離職後に「負担が増した」と感じる人が多いのが実態です。
「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査」によると離職後に負担が増えたと回答した人の割合は、「精神面」について64.9%、「肉体面」について56.6%、「経済面」について74.9%となっています。
出展: 「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査」 (平成24年度厚生労働省委託調査)
負担が増える理由として、離職して収入がなくなったことで介護サービスを利用する費用が賄えなくなることや、好きな仕事・やりがいがある仕事を辞めたことで気分転換の機会をなくしてしまったことが挙げられます。
老後資金が減る
離職すると収入がなくなるため、貯蓄を取り崩して生活することになります。
介護には大人用おむつなどの介護用品の費用がかかるため、離職前に想像していたより出費がかさむことが多くなります。
自身の老後資金を取り崩して介護費用にあてるケースもあり、介護を乗り切っても自身の老後資金が十分に残らない場合があります。
再就職が困難
介護離職者の再就職状況をみると、約50%の人が正社員として再就職している一方で、約25%の人が再就職できずに無職のままです。
出展: 「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査」 (平成24年度厚生労働省委託調査)
いったん離職すると、介護が終わった後も離職前の収入を得るのは難しく、4人に1人は再就職もままならないというのが実態です。
再就職できず生活が困窮し生活保護に頼らざるを得なくなるケースもあります。
介護離職の原因とその理由
仕事と介護の両立が難しい職場環境
「仕事と介護の両立に関する労働者アンケート調査」によると、介護離職の理由は「仕事と手助け・介護の両立が難しい職場だった」が一番多く、約6割を締めています。
離職した人の約5割は「仕事を続けたかった」とも回答しており、仕事を続けたいのにやめざるを得なかったという切実な事情がうかがえます。
介護の知識不足・準備不足
介護離職の理由で職場環境の次に多い理由は、「自身の心身の健康状態が悪化したため」(約3割)、「自身の希望として手助け・介護に専念したかった」(約2割)となっています。
介護は、出産・育児とは異なり、事前の準備期間がないまま直面するケースがほとんどです。
介護に関する知識も準備も不十分なまま急に介護負担がのしかかり、心も体も疲弊すると、つい「仕事を辞めて介護に専念したほうが楽なのでは?」と考えてしまい、離職に踏み切ってしまう。そんな状況がうかがえます。
介護離職の予防、防止策、改善策
介護離職の予防、防止策、改善策には、次のような対策があります。
- 介護の準備
- 介護支援制度の活用
- 介護サービスの利用
- 働き方の調整
介護の準備
高齢の親や親族を持つ人なら、誰しも介護に直面する可能性があります。
日頃から準備しておくことで、いざ介護に直面したときに慌てずに対応でき、介護離職を避けることができます。
具体的には次のような準備をしておくと安心です。
- 自分の会社の介護支援制度を確認しておく
- 済んでいる地域にどのような介護サービスがあるのかを調べておく
- 介護について家族と話し合い、協力体制を確認しておく
介護支援制度の活用
政府は「介護離職ゼロ」を目指して、介護支援のための制度を整備しており、育児・介護休業法で以下の制度を定めています。
介護休業制度
介護休業制度は、労働者が要介護状態にある家族を介護するために休業を取得できる制度です。
休業できる日数は対象家族1人につき93日であり、その日数を最大で3回に分割して取得可能です。
以下のいずれにも該当すれば介護休業を申請することができ、事業主は申請を拒むことはできません。
- 同一の事業主に1年以上雇用されていること
- 介護休業の取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間に、労働契約が満了することがあきらかでないこと
介護休業中は、雇用保険制度から休業前の賃金の67%が「介護休業給付金」として支給されます。
申請は、介護休業を終了する翌日から2カ月後の月末までに、勤務先経由でハローワークに申請します。
介護休業制度のねらいは、休業して介護に専念することではありません。
介護サービスに申し込んだり介護体制を整えたりするといった、仕事と介護を両立するための準備にあてる期間として活用することが重要です。
介護休暇制度
要介護状態にある家族の介護や世話をする人は1年度において5日(対象家族が2人の場合は10日)を限度として、介護休暇を取得することができます。
年次有給休暇とは別に取得できますが、介護休暇中の給与に関しては法律で定められていないため、有給か無給かは企業によって異なります。
時間外労働の制限
要介護状態にある家族を介護する人は、事業主に時間外労働の制限を請求することができます。
従業員から時間外労働制限の請求を受けた事業主は、1ヶ月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働をさせることはできません。
介護サービスを利用する
自分や家族だけで介護を行うのに大きな負担を感じたら、無理をせず介護サービスの利用を検討しましょう。
デイサービスや老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などのさまざまな介護サービスがあります。
お住まいの自治体の福祉課に相談すれば、介護サービスを紹介してもらえますし、厚生労働省が運営する介護サービス公表システム(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)で検索することもできます。
働き方の調整
フルタイムで働くことの負担が大きい場合は、勤務先に働き方の調整を相談しましょう。
時短勤務や短日数勤務、在宅勤務、フレックスタイムなどを活用できれば、仕事の負担を減らし介護との両立をしやすくなります。
介護離職防止に向けての取り組み事例
全国の企業が、介護離職防止に向けてさまざまな取り組みを実施しています。
その中の一例を紹介します。
事例1:花王
花王では、従業員の介護負担を軽減するため、法定以上の介護休業・休暇制度、短時間勤務制度等、柔軟な働き方に関する制度を整備していて、2015年の1月からは時間単位の有給休暇取得も可能にしています。
1時間単位の有給休暇は、病院への付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせなどに活用でき、1日の有給休暇を消化しなくてもすみます。
事例2:メルカリ
メルカリでは介護に関わる従業員の経済的支援に力を入れていて、国から賃金の67%を受けられる介護休業給付金に、残りの33%を会社が付加することで100%保障を実現しています。
また、介護休業から復職する際に、復職一時金を支給しています。
まとめ
介護離職という選択は、後悔するケースが多いため、避けるべきです。
とはいえ仕事と介護の両立は体力的にとても大きな負担がかかり、いつまで続くかわからない介護を自分や家族だけで抱え込んでしまうと、心も体も疲弊してしまいます。
介護で大切なことは負担を分かち合うことです。
そのためには、国の制度や会社の制度を最大限活用する、自治体の福祉課にも相談しながら自分や要介護者にあった介護サービスを利用する、会社に相談して無理のない働き方を選択するなど、積極的に周囲の支援を受けることが重要です。
国や会社にどのような制度があるか、お住いの地域にどのような介護サービスがあるかを事前に調べ、介護に備えておきましょう。
下記のサイトも参考にしてください。
介護離職ゼロ ポータルサイト(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html
介護サービス公表システム(厚生労働省)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
国内の介護離職問題だけでなく、その他の社会問題について詳しく知りたい方は【最新版】日本が抱えている社会問題(社会課題)とは?の記事を是非読んでみてください。
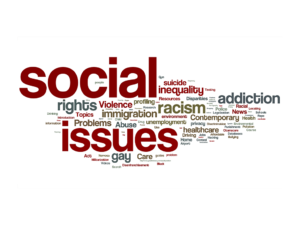
これらの社会問題の解決に向けたヒントや取り組み、この記事で紹介されていない国内における問題などがあれば、当サイトの提案フォーラムに投稿してみてください。
最初は少数な提案意見でも、みんなの声が集まれば、大きな声として社会に届くかもしれません。