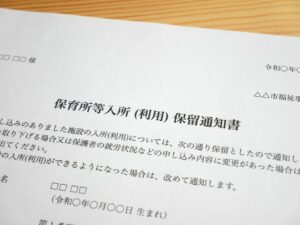日本は、人口の約3割が65歳以上という超高齢社会に突入しています。
高齢者が増えたことで社会問題化した課題の一つが、老老介護・認認介護です。
介護は多くの人がいずれ直面する問題であり、老老介護・認認介護も決して他人事ではありません。
本記事では、老老介護、認認介護の現状や対策について解説します。
老老介護・認認介護とは
老老介護とは、65歳以上の高齢者の介護を高齢者が行っていることをさします。
例えば、65歳以上の妻を65歳以上の夫が介護しているケースや、65歳以上の親を65歳以上の子が介護しているケースが老老介護にあてはまります。
少子高齢化の進行により人口の約3割が65歳以上の高齢者となっている日本では、老老介護になるケースも決して珍しくありません。
自分の周りや自分自身にも差し迫る、身近な問題となっています。
一方の認認介護とは、認知症の高齢者の介護を認知症の高齢者が行っていることをさします。
認認介護は老老介護のなかでも特に深刻な状態です。
認知症患者の中には自分が認知症だと気づいていない人もおり、認認介護になっているという自覚がないケースもあります。
老老介護・認認介護の現状
2019年の国民生活基礎調査によると、要介護者と介護する人がともに65歳以上の老老介護にあたるケースは、要介護者全体の59.7%にのぼり、要介護に認定されている480.8万人のうち約287万人が老老介護の状態にあります。
高齢者人口全体の実に約6.3人に1人が、老老介護の要介護者もしくは介護する側のどちらかの状態にあるのです。
また、山口県で行われたアンケート調査をまとめた論文によると、在宅介護にある老老介護世帯の10.4%が認認介護である可能性が高いことがわかっています。
全国の認認介護の割合が山口県と同程度だと仮定すると、約29万人の要介護者が認認介護の状態にあります。
出典:2019年国民生活基礎調査の概況 – 厚生労働省
出典:令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)- 厚生労働省
出典:【論文】在宅介護における認認介護の出現率 – 第33回愛知自治研集会
老老介護・認認介護が増えている原因
老老介護・認認介護が増えている主な原因は次の2つです。
高齢者の増加
少子高齢化により高齢者の人数は年々増加しており、令和2年には人口の28.8%が高齢者となっています。
高齢者の人数に比例して、老老介護・認認介護の件数も増えています。
核家族化による夫婦のみの世帯の増加
要介護者がいる世帯の核家族化は、この十数年で大きく進んでいます。
核家族世帯の割合は2001年が29.3%だったのに対し、2019年には40.3%まで増加しました。
これにより、介護する人が高齢の夫(妻)である割合も高まり、老老介護・認認介護の件数が増える要因となっています。
老老介護・認認介護のリスク
老老介護、認認介護は、介護する側もされる側も高齢者であることから、介護する側にかかる負担が大きく、無理をして共倒れになってしまうリスクをはらんでいます。
さらに、認認介護になるとそのリスクは非常に大きくなります。
老老介護のリスク
介護する者の身体的負担
介護は、自力で動けない人の体を支えたり、歩くのを補助したりする必要があり、体力を消耗します。
体力や筋力が衰えている高齢者が介護を行う場合、その身体にはとても大きな負担がかかり、消耗して体調を崩したり、怪我をしたりするリスクがあります。
介護する側が怪我などで倒れてしまうと、介護する人がいなくなってしまい、介護が立ちゆかなくなってしまいます。
介護する者の精神的負担
介護は、体力の消耗に加えて精神的な負担ものしかかります。
介護に手一杯になると自分の時間が持てなくなり、外出もできなくなるため家族以外の人と会って話す機会も無くなってしまいます。
介護のストレスを解消する機会が持てないことから、鬱状態や認知症になってしまうケースや、要介護者への虐待といった事件に発展してしまうケースもあります。
認認介護のリスク
認認介護は、介護する側もされる側も認知症の症状があることから、老老介護以上のリスクを抱えています。
食事や服薬の管理ができない
認知症による記憶障害があると、食事を取り忘れたり薬を飲ませ忘れたりといったことが頻繁に起こる可能性があります。
その結果、栄養管理や薬の服用が適切に行われず、要介護者の健康を害する可能性が高くなります。
緊急事態の対応ができない
認知症になると判断力も低下してしまいます。
そのため、要介護者の体調が急変した場合などに救急車を呼ぶなどの適切な判断・行動がとれなくなってしまい、要介護者の命に関わる事態に発展してしまうリスクがあります。
虐待のリスクが高まる
認知症は、鬱や怒りっぽくなるといった症状を伴うこともあります。
介護する側が認知症によりイライラしやすくなってしまうと、要介護者に当たってしまうなど虐待のリスクが高まってしまいます。
老老介護・認認介護の対策
老老介護、認認介護の対策として最も重要なことは、介護を家族だけで抱え込まないことです。
家族だけで抱え込んでしまうと、負担が家族だけにのしかかり、家族が倒れたときに介護する人がいなくなってしまいます。
そのような事態を回避するために、厚生労働省は地域包括ケアシステムの構築を進めており、その一環として各地域に地域包括支援センターを設立しています。
家庭内での介護に少しでも負担を感じたら、お近くの地域包括支援センターの総合相談窓口に相談しましょう。
地域包括支援センターには、ケアマネージャーや社会福祉士、保健師が配置されていて、介護保険サービスの相談や適切なケアプランの相談ができます。
家族だけによる介護から介護保険サービスの利用へと移行することで、老老介護の負担を軽くし、リスクを低減させることができます。
介護保険で利用できるサービスには次のようなものがあります。
ケアマネージャと相談して、これらのサービスを組み合わせて利用するのも介護負担の軽減に有効です。
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、要介護者の食事や入浴、排泄の世話といった身体介護や、掃除、洗濯、買い物といった生活支援を行ってくれるサービスです。
通院などの移送サービスを提供している事業所もあります。
通所介護(デイサービス)
利用者をデイサービスの施設に送迎し、日帰りで施設での食事、入浴、運動などを提供してくれるサービスです。
施設では、高齢者同士の交流もできるため、自宅に引きこもりがちな要介護者の孤立感を和らげることができます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
利用者が、介護老人福祉施設で短期間(最長30日)生活でき、施設での食事、入浴などの生活支援や運動などの機能訓練を提供してくれます。
デイサービスと同様、施設での高齢者同士の交流もできます。
介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)
在宅復帰を念頭に入所でき、入浴や食事などの生活支援や、運動などの機能訓練、療養上の世話を提供してくれるサービスです。
まとめ
紹介してきたとおり、老老介護・認認介護は介護する側にとっても要介護者にとってもリスクが大きく、できる限り回避すべき問題です。
そのためには、介護を家族だけで抱え込まず、介護保険サービスなどを利用して第三者の助けを得ることがとても重要です。
何か困ったことがあったり、介護状況に変化があって負担が増したりした場合は、地域包括支援センターや担当のケアマネージャーに相談し、負担を軽減するケアプランを構築しましょう。
介護は家族で行うものという思い込みを捨てることが、老老介護・認認介護からの脱却の第一歩です。
老老介護・認認介護の問題だけでなく、その他の社会問題について詳しく知りたい方は【最新版】日本が抱えている社会問題(社会課題)とは?の記事を是非読んでみてください。
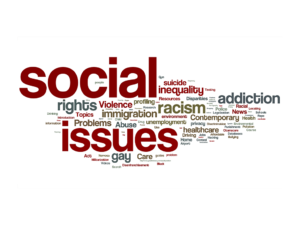
これらの社会問題の解決に向けたヒントや取り組み、この記事で紹介されていない国内における問題などがあれば、当サイトの提案フォーラムに投稿してみてください。
最初は少数な提案意見でも、みんなの声が集まれば、大きな声として社会に届くかもしれません。